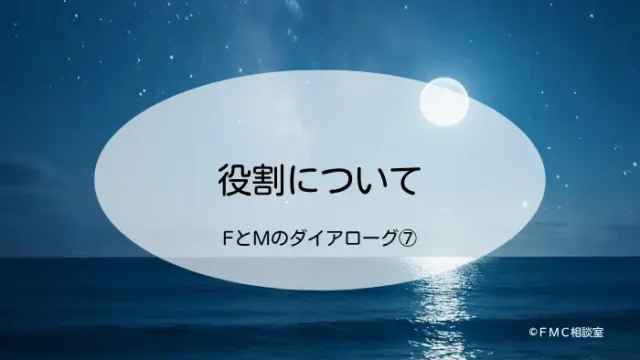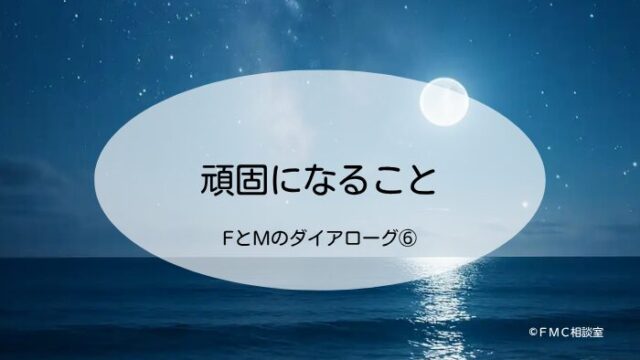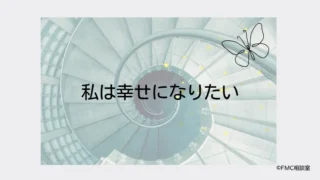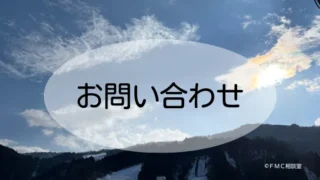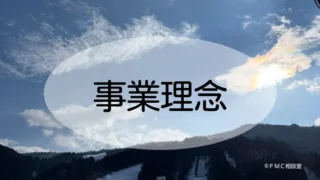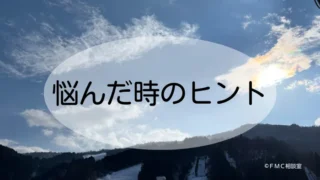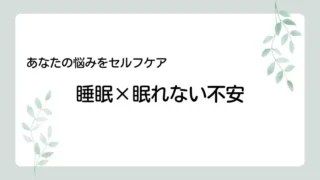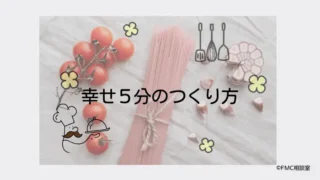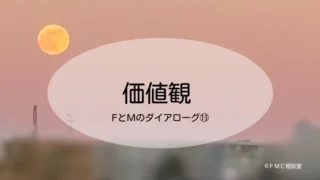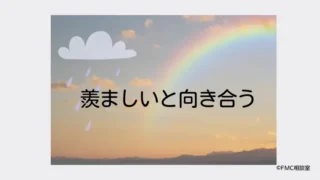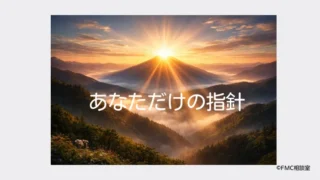FとMのダイアローグ①
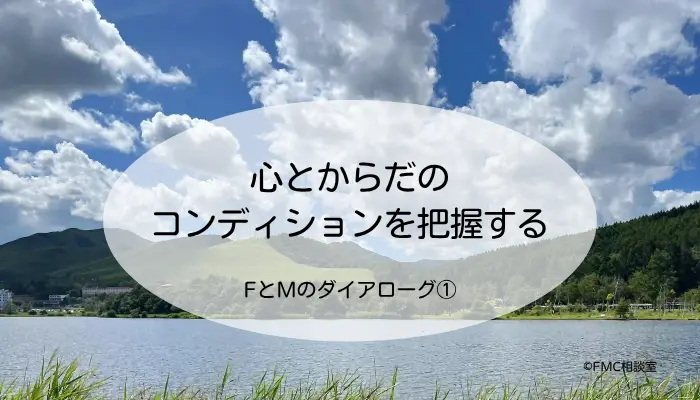
F
私は日々悩みながら働いています。
悩みは家事育児と仕事の両立、介護、健康や生活のこと、挙げていけばきりがありません。
そんな中でも仕事として相談に向かうとき、ここ10年ほど習慣にしていることがあります。
それは毎日必ず心とからだのコンディションを把握することです。
具体的には、仕事に向かう道の途中、決めた場所で必ず自分に問いかけます。
“今日の体調はどうかな?”
“気分はどんな感じかな?”
“今日のコンディションは10点中何点?”
昨日夜中に起こされて眠れなかった6点の日は“今日は無理をしないでおこう”と労わります。
8点以上のやる気が満ち溢れる日は“今日はやりたかったことにも挑戦してみよう”と奮い立たせます。
自分を大切にすること、それが私のはじまりです。
M
からだのコンディションはある程度理解できますが、心のコンディションをもう少し詳しく教えてほしいです。
F
通勤途中の決めた場所で、直近の一番最初に思いつく出来事から思い返します。
例えば
“ちょっと心配なことがあったし胸がざわざわしているな”
“ここのところ忙しくて職場の空気がピリピリしているから行くの緊張するなぁ”
など
特にネガティブな出来事で生まれた自分の気持ちはしっかりと捕まえておきたいです。
それが、心のコンディションに大きく影響するからです。
意識していない不安定さは私のような対人援助職の場合は特に相手にマイナスの影響を与えてしまうので、意識することが重要です。
あとは心の中だけで毒を吐いておくことはとてもおすすめです。
実際に言動に移せばただの幼い人になってしまいますが、心の本音として、素直な気持ちをちゃんとつぶやいてそっとしまってにやっとしておく(笑)。
例えば
“あ~知ってる長い話ばかりでつまらない会議だな、早く終わらないかな~”
“うわ、こんなふうな年の重ね方はしたくないな!気を付けよう”
“ご高名な先生で偉そうにしてるけどダウトだな”
など、ブラックユーモアみたいなことでしょうか。
若い時はもっとダイレクトな心の叫びとして、怒りや寂しさの心の声を、日記や手帳にも書いて吐き出して整理していました。
書き出すことで整理されるのでおすすめです。
心の真実は自分にしかわからない自分だけのものですから、大切にしていきたいと心がけています。
M
心とからだのコンディションで普段から大切にしていることは何かありますか?
F
からだの声をよく聞いて、素直に過ごすことです。
疲れた時は早く寝る。
ストレスが溜まった時は、信頼できる人に話す。
自分の体を理解して、疲れた時に食べると元気になるものを知っておく。
私の場合はクエン酸ですね。
M
睡眠や食事は自分でコントロールできそうですが、信頼できる人または相談相手が見つからない場合はどのようにすれば良いでしょうか?また、ストレスになる悩みの内容によっては自分だけで消化する方が良いこともあるかと思いますが、どう考えますか?
F
身近な年長者に相談してみてほしいと思います。
ご祖父母がお元気ならぜひ電話をしたり久しぶりに会いに行ってみてください。
私たちの悩みを生き抜いてきた世代なので「ちょっと悩みがあって」と頼ればどんな悩みも受け入れてくれることが多いです。
私は育児がいっぱいいっぱいだった時期、精神的には祖母にとても支えられました。
認知症の祖母が一緒に泣いてくれたこともありました。
職場にベテランのシニア世代の方がいらっしゃるならば、ぜひ悩みをつぶやいてみてください。
そっと優しく拾い上げてくれると思います。
自分だけで消化する方がよい悩みというのは自分と向き合う必要性のある、自己成長のための悩みということでよいでしょうか?とても大切な視点だと思いました。
そういう悩みの時期に私は偶然の新しい出会いを求めるよう意識のアンテナを張ります。
例えば音楽、好きなアーティスト以外にも目に入った新しいジャンルを聴いてみます。
研修会もそれまで興味がなかった分野に参加してみます。
自分だけの消化液のように作用して悩みへのヒントをくれる経験をしてきました。
M
ありがとうございました。
以上、心とからだのコンディションを把握するのテーマでダイアローグしてみました。あなたにとって参考になれば幸いです。
ダイアローグとは、単なる情報交換を超え、参加者同士が相手の意見や考えを深く理解し、共感を深めながら、新たな視点や行動の変化を生み出す「対話」を意味します。
組織では、相手と自分との間に「相互理解」と「共通の理解」を築くためのコミュニケーション手法として用いられ、信頼関係の構築や創造性の育成、組織力の向上に繋がります。
組織をマネジメントする立場にある人にとっては欠かせないスキルです。ただ、センスで乗り切っている人が多いと感じる印象もあるので、具体的な対話で学べるように表現してあります。