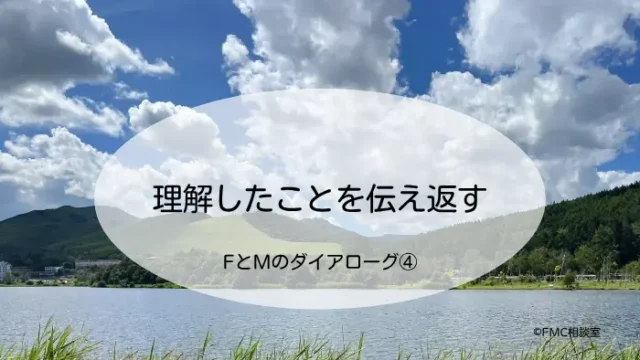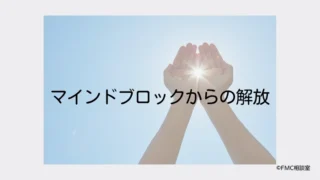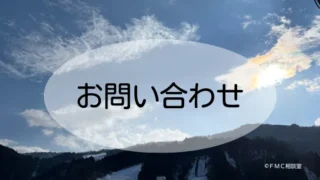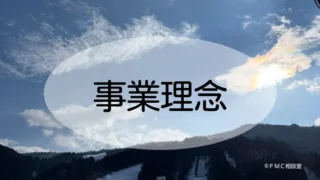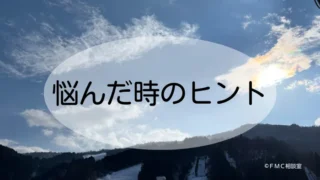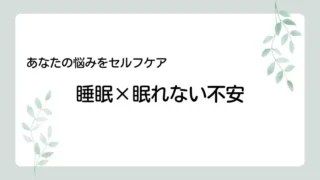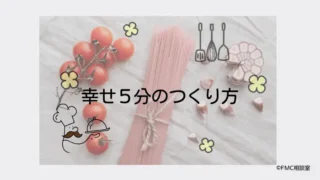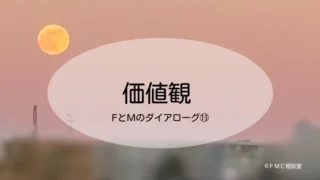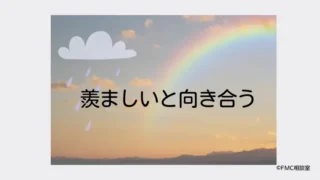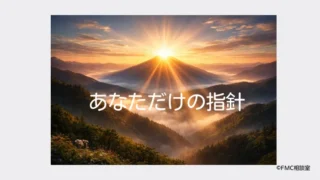FとMのダイアローグ③
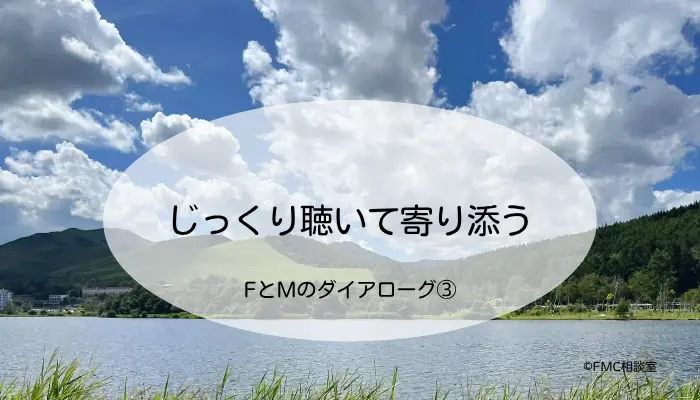
M
今回は「じっくり聞いて寄り添う」をテーマに、ダイアローグします。まずはお考えをご自由に聞かせてください。
F
傾聴というのは、まず、カウンセリングの六条件というものがありまして、、
M
あのっ、難しいのはお断りします
F
え?日常の中でわかりやすく、そうですか。
突然ですが、あなたはずっと集中を向け続けて人の話って聴けますか?
私にはできません。
だいたいの方はそうなのではないでしょうか。
でも短い時間だけでも相手に意識を集中する、ということならどうでしょう。
誰にでもできそうですよね。
行動にするとどうでしょう、自分がもし相談する側だったらと仮定して考えてみてはいかがでしょうか。
例えば相手がスマホを見ながら“うん、うん”と共感している、話してみようと思えますか?
相手が忙しそうに家事をしている、辛そうに疲れた表情をしている・・・“やめておこう”となりますよね。
①相手に目を向け穏やかな表情で
②何かをしながらではなく手を止め体を向けて
③最後まで話を聴く
その姿勢があれば短時間であっても、“聴いて受け止めてもらえた”と感じてもらいやすい気がしています。
M
これが自分は一番難しいと感じます。
誰もが私と同じと思い込んでいたので、答えを探しているならすぐに伝えたいと思い、話の途中でも遮って伝えていた。
それが正義だと思っていました。
そんな人にアドバイスをお願いします。
F
すぐに答えをきけることが助かるという方ももちろんいると思います。
日常の相談がテーマですのでそれもありだと思いますし、私も仕事の相談と日常とでは完全に使い分けています。
その前提の中でご質問のお答えの一つとしては、自分が何で悩んでいるのかを実はよく意識したり言語化したりできないままに相談がはじまることも多々あるということです。
その場合は、相談しようと思った“経緯”をとにかく把握するようにして質問して話を聴いていく、ということになります。
“どのようなことがあって、私に相談してみようと思ったの?”
“いつくらいからそう思っていたの?”
“誰から言われたの?”
“どんなふうに?”
など、5W1H的に状況をなぞっていくように質問をして聴いていく。
そして、一通り確認をして状況がみえてきたら、
“それに対して(そういわれて)、あなたはどういう気持ちだったの(気持ちなの)?”
ここではじめて悩みがはっきりと輪郭をもってくるのですね。
現代は悩みを悩めない人、葛藤できない人が多いといわれていますね。当然、意識化されていないことは言語化はできませんので、大人であってもそこからはじめるという人がかなり多くなってきている印象があります。
M
経緯をなぞることで、お互いの理解が深まりますね。私は相談というより、部下との面談で目標設定する場面があるのですが、言語化できない方が多い印象を受けます。相談者が言語化をうまくできない場合の、じっくり聞いて寄り添うについて、どのように考えて言語化を導き出しますか?
F
やはり現場としてもそう感じられているのですね。予想される状況としては、二通りあるのかなと思いました。
一つは、考えはあるけれども言語化そのものが苦手なタイプという場合。
その場合は一緒に何か資料を見たり、現場をまわりながらの方が言語化が促進される可能性が高いと考えます。
非言語の媒介を意図的に作るということですね。
また、思考がゆっくりでこだわりもあるため言語化に時間がかかるタイプの場合は、一度文章で要点を投げかけ、あとから返答をいただくという方法もあると思います。
もう一つは気持ちや考えが成長過程で言語化につながらないタイプの場合。
自己理解がまだこれからのタイプですね。このような場合は言語化よりも自己探索の体験として、とりあえずやってみてもらうしかないと考えています。
その際、①興味がある分野、②適正、の2点を必ず確認してから、組織の中で最適かつ失敗しても全体の損失が少ないと思われる業務を目標として提案し、スモールステップでトライするよう促します。
自己理解してもらいながら自信をつけていただくことが大切だと思っています。
じっくり心の声を聴いて寄り添うことで言葉を紡いでいく、というスタンスでいます。
M
自分の時間感覚は自分だけのものを意識しながら、じっくり声を聞くことが大切ですね。相手に合わせて方法を変えるのは経験で学ぶことが必要と感じますが、私にとって、また読者の皆さんにとってもヒントになったと思います。「じっくり聞いて寄り添う」を身近な人に試して行けると良いですね。
ダイアローグとは、単なる情報交換を超え、参加者同士が相手の意見や考えを深く理解し、共感を深めながら、新たな視点や行動の変化を生み出す「対話」を意味します。
組織では、相手と自分との間に「相互理解」と「共通の理解」を築くためのコミュニケーション手法として用いられ、信頼関係の構築や創造性の育成、組織力の向上に繋がります。
組織をマネジメントする立場にある人にとっては欠かせないスキルです。ただ、センスで乗り切っている人が多いと感じる印象もあるので、具体的な対話で学べるように表現してあります。