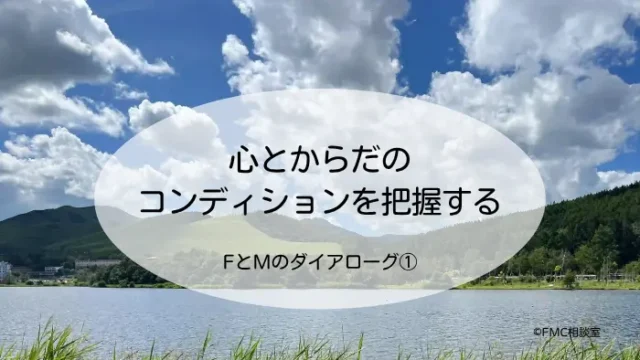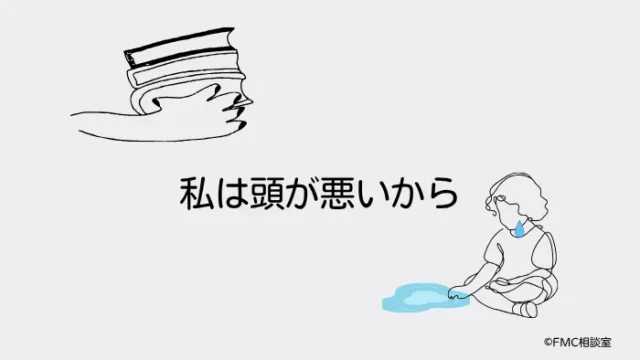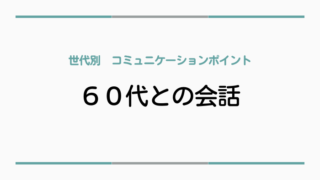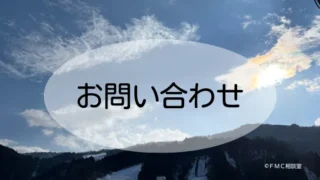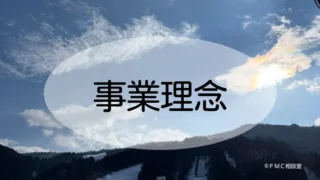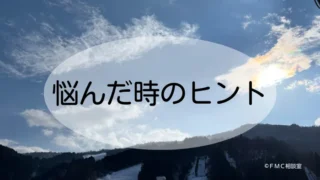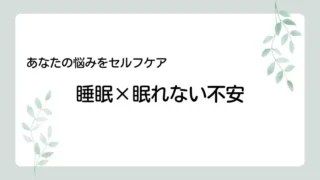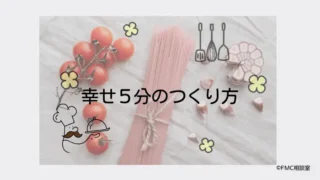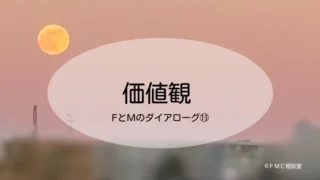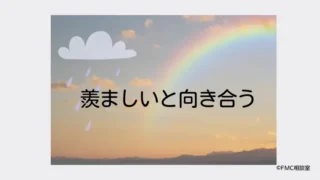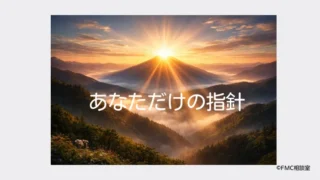FとMのダイアローグ⑥

M
今回はテーマとして「頑固になること」について対話したいと思います。まずはFさんの「頑固になること」という言葉について自由にお話しください。
F
どのような性質もそうですが、頑固にもよい面と悪い面の両面があると思っています。
頑固一徹、初志貫徹、筋を通す、など信念や考えを貫く軸の強さがよい面。こだわりの強い職人気質の方にとても多いですし、頑固がよい形でお仕事に活かされていますね。
一方で、融通がきかない、新しい提案や変化を受け入れにくい、他人の意見を聴かない、というように傾くと悪い面もでてくると思います。
本人よりも周りが関わり方に困ってしまうことが多いのではないでしょうか。その点で頑固は、チームワークと馴染みにくい石のような性質、といってもいいかもしれません。
M
確かに頑固には、良い面と悪い面の両方がありますし、若い頃から何故か持っている価値観の頑固さと、年齢を重ねるに従って生まれてくる頑固さなど複雑性が高い概念ですよね。
今回はチームをまとめる立場視点での話としてお考えください。
私は人それぞれ価値観や運命を持って生まれてきていると考えますが、明らかにその頑固さがあなたの人生を苦しくしていませんか?と感じる場合があります。
何か力になりたいと考えた場合、カウンセリングで本人に気づかせるようなアプローチはありますか?もしあるならそのプロセスを教えていただきたいですし、無いなら、どのようにして本人の幸せに貢献していくのでしょうか?相談にいらっしゃる方は切羽詰まった状態のイメージがあるので質問が適切で無いかもしれません。
F
臨床心理学的な頑固は、几帳面、完璧主義、ケチ、固執、支配などとも関係すると考えられてきています。
ためていき自分の世界だけで完成したがってしまう。他人に委ねたり受け入れたりというのは自分が頑なに守ってきた世界観がひっくり返される可能性があるので変化に対する怖さが生まれやすいと思います。
年齢を重ねれば余計でしょう。なのでミーティングなど大勢の人が集まる場で突然新しい提案なんかがあろうものなら、余計に頑なになってしまうんですね。
あなたの組織にも、強い声量で威圧し自分の意見を通そうとしたり、スパッと話を終わらせてしまったり、怒るような内容ではないのに突然怒り出したりする頑固者はいませんか?その背景にはこういった変化への怖さが湧き上がってきていることもあるかもしれません。
M
会議の中で、新しい提案への拒否を何度も目にしたことが思い出されます。
F
じゃあどうするか、やっぱりこれは『理解を伝える』ことだと私は思っています。
本人から歩み寄ろうとしてくることはまずないですから、頑固者に対峙するときには事前リサーチが鉄則。作品や業績、資料でもこれまで関わった部署の人からの話でもよいので、『何を大切にしてきているのか』を知って、『先回りして理解を伝える』つまり、『あなたの世界観を尊重しているし脅かす存在ではないことを示す』ことが協力関係を築く上で大事なのではないかと考えます。Mさんだったらどういう関わり方をされますか?
M
私も基本的には理解を伝えることに同意します。頑固さの理由として、変化への不安、自己防衛、自己中心主義、言語化できない価値観など、理由は複雑すぎて私は根本の原因は特定できないと考えています。ですので、本人を深掘りして改善を促すことは時間的に難しいとも思っています。そうなると頑固さをチームで生かす方法を提案することから始めることは、安易かもしれませんが、一般的かと感じています。
本人への理解を示してあなたの強みはここだから、それをいかしてほしいと伝える。これが最初のアプローチです。ただ頑固さはチームには理解されない場合が多いので、どこかで歪みが出て、組織が弱体化していくという負のループにはまっていく場合もあります。最初のアプローチは適切か?また、その後についてアドバイスいただきたいです。
F
本人への理解を示して強みを活かしてほしいと伝えることが最初のアプローチ、ということに同じ意見です。
チームへの理解という点について、頑固者には言語化する通訳者の存在が必須だと思います。“Aさんはこういう考えを大切にされてきています”とか、“チームの意見としての〇〇はAさんの以前の業績とも繋がっています”とか、頑固者とチームとを繋ぐ存在が必要になるでしょう。信念があり価値ある頑固者にはこのような対応がベストだと考えます。
一番悩ましいのが、信念があるように見せかけてまだ実は信念をもっていない頑固者ではないでしょうか。その場合は、チームの声を集めて数の多さをもって伝え改善努力してもらう方向に進むのか、諦めてできるだけ穏やかに静かに居てもらう方向にするか、どちらかかなと個人的には思って組織をみています。
M
確かにその通りですね。ちょっと諦めているケースが多い気がします。
組織の力を高めるのはエネルギーのある人に権限や役割を与えることに注力することが肝心だと私は考えています。ただ、職場の仲間が困っているなら支援したいとも思います。
Fさんがもしカウンセリングとして、信念があるように見せかけてまだ実は信念をもっていない頑固者を相手にした場合が相談者としてきた場合は、どのようにカウンセリングをしていくのでしょうか。ゴールは自己理解して言語化できるとしたら。設定は架空で良いので流れを教えていただけるとヒントになると感じます。
F
頑固が人生を苦しくさせているように見えるから支援したいとおっしゃっていましたね。臨床の場でお会いするときには行動や生活の問題が大きくなって個別的専門的アプローチが必要になっていることも多いように思います。そのようなときは職場の案内にそって医療機関や専門職へ繋ぐ視点をもっていただけるとよいかと思います。
きっとMさんが想定しておられるのはもう少し手前というか。でもこのタイプは自分から弱みを見せたり相談してきたりすることは少ないですよね?
もし私だったらと考えると、ユニバーサルデザインと自己分析が頭に浮かびました。制度化されているストレスチェックからもう一歩踏み込んで、社内研修で自己分析や他者理解のワークをするのはどうでしょう。“ジョハリの窓”、“マインドマップ”などは有名ですが、エゴグラムも個人的にはおすすめです。
厚生労働省のホームページから、簡易的な自己診断が可能です。このタイプは周りから助言されるよりも、自分の納得感が優先されることが多いので形式的・客観的にふりかえる機会を作って、自分で自分に介入した方が自己理解しやすいのではと思います。
言語化という点でも、自己評価を大切に考えたいですね。自分軸で達成度や課題点を評価してもらい、そういった資料をもとに個別面談を組みたいです。縦軸を気持ちの変動、横軸を年齢とした“自分史グラフ”などをカウンセリングで時々書いていただくのですがそういったイメージです。
何歳からでも大丈夫、自分の人生を取り戻して創造していってほしいと願います。その人らしい健やかさで、人生満喫しながら幸せに働いていただきたいですね。
M
話を伺って、腹に落ちたと感じます。人それぞれ今の役割を演じていますから、役割が適応する形で変化できるような問いを与える会話ができると良いですね。その際、資料を活用してみようと思いました。とっても難しそうですが<笑>、自分のできることから取り組みたいと思います。アドバイスありがとうございました。
ダイアローグとは、単なる情報交換を超え、参加者同士が相手の意見や考えを深く理解し、共感を深めながら、新たな視点や行動の変化を生み出す「対話」を意味します。
組織では、相手と自分との間に「相互理解」と「共通の理解」を築くためのコミュニケーション手法として用いられ、信頼関係の構築や創造性の育成、組織力の向上に繋がります。
組織をマネジメントする立場にある人にとっては欠かせないスキルです。ただ、センスで乗り切っている人が多いと感じる印象もあるので、具体的な対話で学べるように表現してあります。